
電気新聞ゼミナール(337)
進化心理学に基づくナッジは省エネ行動変容を実現できるか?
世代間支援の強調により環境意識を向上
進化心理学とは、人間の根源的な心理反応を生物学的な合理性に基づいて明らかにする研究分野である。電力中央研究所では、カナダのセント・メリーズ大学等との共同研究を通じて、行動経済学におけるナッジ(ちょっとしたきっかけによって望ましい選択を促す介入方策)を、進化心理学の知見に基づいて効率的に設計する研究を進めてきた。その成果として、過去から受け継がれてきた恩恵(以下、世代間支援)を強調したメッセージによって、各種技術への抵抗感が緩和され、プラスチックの再利用や洋上風力発電の受容性といった、種々の環境意識が向上することを明らかにしてきた。
データ要らずのメッセージで行動変容を促進
省エネ行動変容を目的とした既存のナッジで最も著名なのは、他者と比較してエネルギー消費量が多いことを伝えるメッセージ手法である。例えば電力料金票に、対象の顧客の消費量と併せて、平均的な顧客や省エネが進んでいる顧客の消費量を棒グラフで比較提示することで、3%程度の省エネ効果が得られることが知られている。
しかし、比較のグラフを作成する際、単純ではあっても消費量データを蓄積して計算する必要があり、そのための計算資源はサービス上のコストとなる。一方で、世代間支援を強調したメッセージは、文章とイラストによる工夫のみで構成される。したがって、データ処理は不要となり、より低コストで幅広い対象に情報提供できる利点がある。
省エネ行動を確認
こうしたメッセージが意識レベルのみではなく、実際に行動変容を促進できるか否かはこれまで明らかでなかった。そこで、セント・メリーズ大学、芝浦工業大学、早稲田大学との共同研究により、省エネ促進を目的とするメッセージ(図)を新たに作成し、2024年夏季に日本国内の14,000人以上のユーザを対象とした調査を実施した。世代間支援を強調したメッセージによって、実際に省エネ行動がどのように促進されるかを分析した初の事例となる。
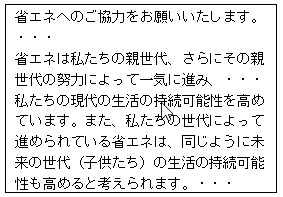
図 省エネ行動変容を促進するナッジの例
世代間支援を伝えることで、電力消費量を削減できるだけでなく、
職場など自宅以外での省エネ意欲も向上させることができる。
省エネを呼び掛ける単純なメッセージと比較した効果検証の結果、追加的に平均約3.3%の省エネ効果があることが明らかになった。また、メッセージ提供は家庭を対象として行われたものの、職場など自宅以外での省エネ行動に対する意欲も有意に向上した。その他、省エネが金銭的に得であることを強調したメッセージと比較すると、自分のためではなく、血縁者や未来の世代のために省エネをしようという動機が強く現れることも明らかになっており、より長期的な省エネ効果も期待される。さらに、他者比較によって同調圧力と捉えられるリスクも回避できる。
自治体オフィスでの社会実装
現在、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)下で、自治体オフィスでの省エネを目的として、開発したメッセージを利用した情報提供システムの社会実装を進めている。消費量データを必要とせず、幅広い対象にリーチできる利点があるため、中小規模のビルなど、設備の直接制御が難しい事業所においても省エネの促進が期待できる。これによって、家庭に比べると検証事例が少ない事業所における、省エネナッジの知見の蓄積にも貢献する。
なお、本社会実装では、スマートフォンを活用して、より個別性を高めたメッセージを配信することも予定している。さらに、消費量データが利用可能な場合も想定し、各事業所に適したタイミングでメッセージを配信することによって、より効果的に省エネを促進することも検討予定である。
電気新聞 2025年7月23日掲載



