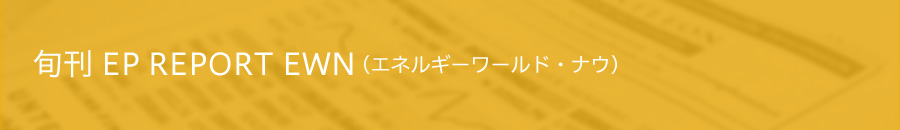
旬刊 EP REPORT EWN(第2149号)
ベトナムなどが最新投資計画 電力脱炭素化と需要増に対応
民間投資拡大が計画実現のカギに
ベトナムとインドネシアで相次いで電力投資計画の最新版が公表された。両計画はいずれも、パリ協定の下で政府が掲げる長期脱炭素目標を反映したもので、経済成長に伴う電力需要増加への対応と電力の脱炭素に向けた道筋が具体的に記載されている。

ベトナムの電源構成とインドネシアの新設電源の構成
ベトナムでは、10年ごとに政府が国家電力開発計画を策定する。本稿の執筆時点の最新版は、政府が掲げる2050年ネットゼロ目標の達成に向け、30年までの投資計画と50年のビジョンを示した、第8次国家電力開発計画(PDP8)である。今年4月15日、ベトナム政府は、足元の情勢変化への対応として、23年5月に策定したPDP8の改訂版を公表した。
PDP8 改訂版では、今年から30年までの6カ年を実施期間とし、30年時点の設備容量の見通しが示された。
まず、経済成長に伴う電力需要増をまかなうため、総設備容量は今年の89.4GWから30年までに183.3~236.4GWに増加し、全体の約6割を再生可能エネルギーが占めることとされた。主な内訳は、陸上・沿岸風力26.1~38.0GW、太陽光46.5~73.4GW、水力33.3~34.7GWである。加えて、洋上風力6.0~17.0GWが、30年から35年までの導入見通しとして示された。
再エネの大規模導入に伴い、30年時点の蓄電容量は、バッテリー10.0~16.3GW、揚水2.4~6.0Gとされた。
PDP8改訂版では新たに、35年までのビジョンとして、原子力発電6.4Gの新設が含まれた。これは、昨年から今年にかけて政府が原子力への投資方針を決定したことを受けたものである。
化石燃料の見通しも示され、天然ガスは、石炭を置き換える重要なベースロード電源として位置付けられた。ベトナムでは元々、国内産天然ガスを発電に使用してきたが、計画では輸入LNGの拡大により30年の設備容量を33.4~37.5GWとした。一方、石炭は50年早期退役に向けて現在建設中の5地点を30年までに運開することを求めた。その上で、30年の設備容量を31.1GWとした上で、25.8GWについては、50年までにバイオマスやアンモニアへの完全に燃料転換することとした。
インドネシアでは、政府が策定する国家電力総合計画(RUKN)を踏まえ、国営電力会社(PLN)が10年単位の電力供給事業計画(RUPTL)を策定する。今年5月26日、PLNは、RUPTL2025―2034を公表した。これは、60年ネットゼロ目標と45年の先進国入りを掲げた国家ビジョンを踏まえたものである。
RUPTL2025―2034では、今年から2034年までの新設電源の容量が示され、全体の約6割が再エネとされた。主な内訳は、風力7.2GW、太陽光17.1GW、水力11.7GW、地熱5.2GWである。また、実証事業という位置付けで原子力0.5GWも含まれた。
蓄電の新設は、バッテリー6.0GW、揚水4.3GWである。
計画には化石燃料も含まれている。34年までの新設については16.6GWで、内訳はガス10.3GW、石炭6.3GWである。このうち、12.7GWは10カ年の最初の5年間(今年から29年)に実施される。既に建設が進んでいる案件が複数あることに加え、足元の電力供給を確保するためである。
さらに、両者の計画には、再エネの導入と電力需要の拡大に対応するための送配電の新設・増強も含まれており、これら全体をまかなうためには莫大な投資が必要となる。
ベトナムではPDP8改訂版公表以降、26年から30年までの投資額を1363億ドル(発電1182億ドル、送配電181億ドル)と見積もった。同様にインドネシアでは、今年から34年までの投資額を1855億ドル(再エネ1052億ドル、火力282億ドル、送配電353億ドル、その他168億ドル)と見積もった。
これらを当事国の国営電力会社だけでまかなうことは現実的でないため、両者の計画はいずれも、IPP(独立系発電事業)や国営電力との合弁などを通じて民間投資を呼び込むことを前提としている。とりわけ、脱炭素のカギを握る再エネでは民間投資の役割が大きく、インドネシアの計画においては、新設電源の73%をPLN以外のIPPが担うことが明記された。
計画達成に向けた民間投資を呼び込むには、当事国だけでなく、先進国政府や開発金融機関、輸出信用機関、市中金融機関の連携による投資環境の整備が不可欠である。日米欧による「公正なエネルギー移行パートナーシップ(JETP)」による支援は、再エネ導入と石炭早期退役、送配電投資を加速させる前提と位置づけられている。
加えて日本は、アジアゼロエミッション共同体(AZEC)の下、再エネや水素・アンモニア混焼、CCUS(CO2回収・利用・貯蔵)、送配電など幅広い分野で協力を進めている。こうした取り組みを継続・強化し、安定した投資環境を構築・改善していくことが、当事国の脱炭素と経済発展を後押しするとともに、日本企業に新たな事業機会をもたらすカギとなる。
旬刊 EP REPORT 第2149号(2025年7月21日)掲載
※発行元のエネルギー政策研究会の許可を得て、記事をHTML形式でご紹介します。

