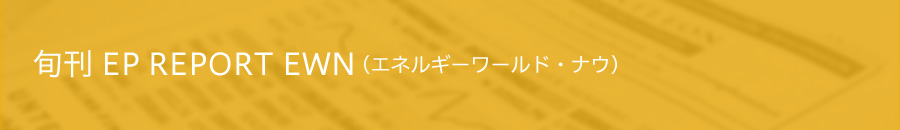
旬刊 EP REPORT EWN(第2158号)
ドイツがCCS推進で法改正 商用化と海底下貯留を解禁
CCSガス火力にも慎重な容認姿勢
ドイツでは、2012年制定の「二酸化炭素貯留法(KSpG)」の改正案「二酸化炭素貯留・輸送法(KSpTG)」が、今年8月6日に閣議決定され、9月8日に連邦議会へ提出された。成立すれば、長らく停滞していた同国のCCS(CO2回収・貯留)政策の転換点となる。現在は委員会審議に入り、参議院も修正意見の提示にとどまることから、骨格は維持されたまま成立に向かう見込みだ。主な改正内容は3点である。

KSpTGの主な改正内容
第一に、研究・実証目的に限定されていたCCSを商業目的も可能にする枠組みとなる
第二に、CCS関連インフラの位置付けの変更である。CO2パイプラインを連邦許認可対象インフラとして明確化し、貯留設備と共に「優先的公共利益」に指定する。これにより、許認可・用地取得・訴訟対応などの手続きが簡素化・迅速化され、投資の法的確実性が高まる。また、 既存のガスパイプラインなどをCO2輸送に転用する場合、その改造の程度に応じて新規の許認可を経ずに利用できる枠組みも整備される。さらに、ドイツ領内を通過する越境CO2パイプラインも国内と同等の手続き・安全規制の枠内で扱われ、CO2の輸出入を扱う案件であってもドイツ側では既存の国内許認可のもとで申請・審査できる仕組みとなる。
第三に、貯留に関する規制の見直しである。これまで実質的に想定されていなかった海底下貯留は、排他的経済水域と大陸棚下において可能になる。陸上貯留は、連邦一律の解禁は見送られ、従来の「州が禁止すれば実施不可(オプトアウ卜)」から「州が許容した場所以外は実施不可(オプトイン)」に転換される。
法改正の背景には、政策環境の変化がある。10年代初頭、ブランデンブルク州などで計画されたCCS実証プロジェク卜は、地下貯留の長期安全性や石炭火力の延命への懸念から住民の反発や地方議会の反対決議が相次ぎ、停滞した経緯がある。結果、12年のKSpG(現行法)は、商業規模の展開を許容しない内容となった。一方で、21年に法制化された「45年気候中立」目標と整合を図るにはセメントなどの不可避排出への対処が不可欠となり、産業界からCCS解禁を求める声が強まった。また、周辺国ではノルウェー政府主導のノーザンライツプロジェクトが域外からのCO₂受け入れ・海底下貯留を進めるなど、ドイツ発のCO₂を北海で貯留する選択肢も現実味を増している。さらにEUのネット・ゼロ産業法は「30年までにEU全体で年間5000万tの注入能力確保」を掲げ、貯留サイト開発と越境輸送インフラ整備を後押ししている。今回の改正案は、こうした動向と歩調を合わせ、海底下貯留の解禁と陸上オプトインの組み合わせによって、10年代の教訓(社会的受容への配慮)を踏まえつつ停滞した国内CCSを進める狙いがある。
改正案と並行して、CCSに対する 財政支援にも動きがみられた。「気候保護契約」は、CO2削減の達成度に応じて15年の差額補填(CCSコス卜と炭素コストの差額を補償する炭素差額決済)を行う枠組みである。今年10月には、次回(26年)入札の予告が行われ、初回(24年)からの見直しとして、CCSを明示的に対象に含める方針が示された。CCS実装の基盤が法制度と財政支援の両面で整い始めている。
発電部門のCCS適用については、慎重姿勢を保ちながらも容認方向に転じつつある。現状ではCCS適用の優先度は、不可避的に排出が生じるセメン卜・化学など産業部門に置かれ「気候保護契約」もこれらが対象である。石炭火力については、改正案で石炭由来CO₂のパイプライン接続が禁止され、事実上CCSの対象外とする方針が明記された。「CCSによって石炭の段階的廃止を遅らせない」という立法趣旨に基づく。
一方、ガス火力へのCCS適用は改正案で明確には禁止されておらず、法的には排除されていない。9月26日に連邦参議院(上院)は、本改正案に対する意見書で「石炭火力へのCCS接続禁止規定をガス火力にも適用すべき」と要望し、「どの排出が『不可避排出』に該当するのかを明確に定義し、化石燃料の延命につながらないようにすべきだ」と指摘した。
これに対し政府は、10月8日付の回答でこの提案を退け「接続禁止は石炭火力に限る。石炭火力は段階的廃止が定められていることが根拠であり、ガス火力でのCCSの扱いは策定中の『発電所戦略』において検討する」と回答した。
従来、ドイツにおけるガス火力の脱炭素化は、水素専焼の義務化が基本方針であったが、5月に発足したメルツ政権は その義務化を柔軟に運用する姿勢を示している。政府は、9月公表の行動計画において、水素への転換を見据えたガス火力の優先順位を高くしつつも「技術中立な」容量市場を27年までに導入するとし、また、CCS支援の対象に新たに 発電所を含める方針を示した。これらは CCSガス火力を容認する方針を示唆する。
発電分野は技術中立とし産業中心で進めるドイツのCCS推進は、英国(ガス火力CCSを系統の調整力として制度的に明確に支援)、米国(45Q税額控除で発電を含むCCSを横断的に後押し)とは異なるアプローチであり、こうした違いは各国の脱炭素の行方を占う上で注目点の一つである。
旬刊 EP REPORT 第2158号(2025年11月1日)掲載
※発行元のエネルギー政策研究会の許可を得て、記事をHTML形式でご紹介します。

